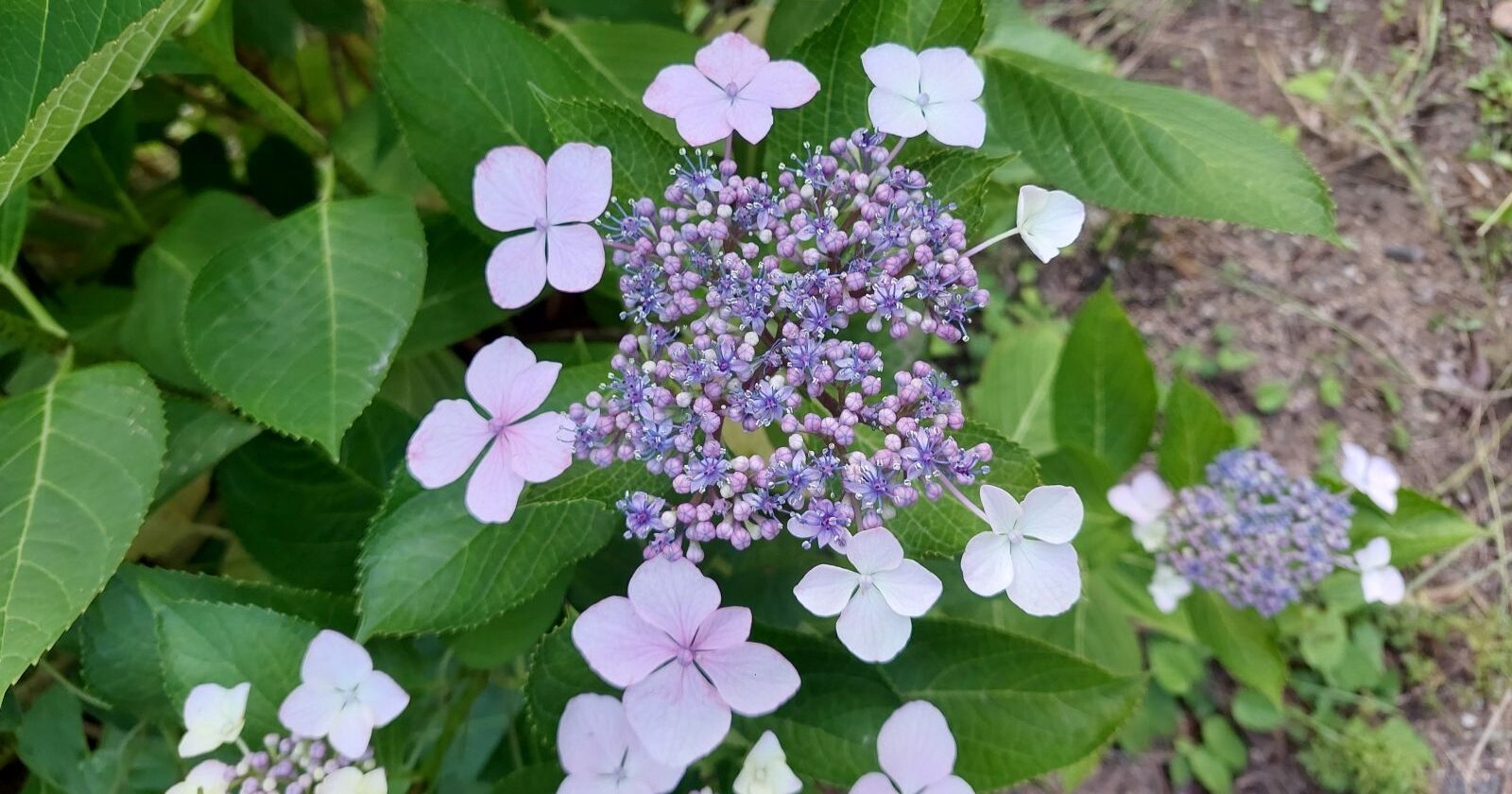今回は、相続時精算課税と生前贈与の加算を確認してみましょう。
生前贈与の加算
相続などで財産を受け取った人(相続人)が相続の開始前7年から3年以内に、亡くなった方(被相続人)から贈与で財産を受け取った場合に、贈与で受け取った財産を相続税の計算に追加する特例があります。生前贈与の加算といいます。
生前贈与の中には、相続のときに贈与税を精算する方法(相続時精算課税)があります。相続時精算課税を選択した場合、選択した後に贈与で受け取った財産は相続税の計算の計算に追加する必要があります。
相続時精算課税との関係
贈与税を相続のときに精算する方法(相続時精算課税)を選択した場合、
・贈与した財産の金額
・贈与税など
が相続税の計算に追加されます。
この追加される規定(読替規定)に、生前贈与の加算があります。
読替規定のうち、生前贈与の加算に関する部分を確認してみましょう。
第十九条第一項中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産」と、実際に読み替えてみましょう。
(相続開始前七年以内に贈与があつた場合の相続税額)
第十九条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産及び第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を除く。)に限る。以下この条及び第五十一条第二項において同じ。)(以下この項において「加算対象贈与財産」という。)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額(加算対象贈与財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。読み替える前の規定
「特定贈与財産を除く。」
(特定贈与財産は、婚姻期間が20年以上の配偶者に関する特例の財産)
読み替えた後の規定
「特定贈与財産及び第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を除く。」
「第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産」は、相続時精算課税の対象となる財産のことです。
「除く」とありますので、相続時精算課税の対象となる財産は、生前贈与の加算の対象から外れます。
生前贈与の加算がある場合
・相続時精算課税で相続税に加算される贈与
・生前贈与で相続税に加算される加算
が重複する場合は、相続時精算課税が優先されます。
反対に重複しない場合は、生前贈与の加算の対象となります。
参考となる基本通達を確認してみましょう。
長いので分けて確認します。
相続税法基本通達19-11、相続時精算課税適用者に対する法第19条第1項の規定の適用
19-11 相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産については法第19条第1項の規定の適用はないが、・相続時精算課税を選択した人(子)を「相続時精算課税適用者」
・相続時精算課税の対象となる贈与をした人(親)を「特定贈与者」
といいます。
相続時精算課税の対象となる財産については、
生前贈与の加算(相続税法第19条第1項)の規定は適用されません。
続きを確認してみましょう。
当該特定贈与者の相続に係る加算対象期間内で、かつ、相続時精算課税の適用を受ける年分前に当該相続時精算課税適用者が、特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した財産(年の中途において特定贈与者の推定相続人となったときには、推定相続人となった時前に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産を含む。)については、同項の規定により当該財産の価額を相続税の課税価格に加算することとなることに留意する。加算対象期間内は、相続の開始前7年から3年以内のことです。
相続時精算課税の適用を受ける年分「前」に当該相続時精算課税適用者(子)が、特定贈与者である被相続人(親)からの贈与により取得した財産(省略)については、同項の規定により当該財産の価額を相続税の課税価格に加算することとなることに留意する。
相続時精算課税を選択する「前」の贈与については、生前贈与の加算の対象となります。
カッコ書きは、年の途中で養子(推定の相続人)になった場合について記載されています。養子縁組の前は、相続時精算課税の対象から外れるため、生前贈与の加算の対象となります。
続きを確認してみましょう。
また、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった者であっても、その者が当該被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者であり、かつ、当該被相続人から加算対象期間内に贈与により取得した財産(相続時精算課税の適用を受ける財産を除く。)がある場合においては、その者については、同項の規定の適用があることに留意する。(平15課資2-1追加、令5課資2-21改正)当該被相続人(親)から相続又は遺贈により財産を取得しなかった者(子)であっても、
その者(子)が当該被相続人を特定贈与者(親)とする相続時精算課税適用者(子)であり、かつ、
当該被相続人(親)から加算対象期間内に贈与により取得した財産(相続時精算課税の適用を受ける財産を除く。)がある場合においては、その者(子)については、同項(法第19条第1項、生前贈与の加算)の規定の適用があることに留意する。
例外で、相続などにより財産を取得しなかった人(子)であっても、相続時精算課税を選択して、加算対象期間内に贈与で財産を受け取る場合は、生前贈与の加算の対象となります。
カッコ書きで「相続時精算課税の適用を受ける財産を除く。」とありますので、
・相続時精算課税の対象となる財産 → 相続時精算課税で加算
・相続時精算課税の対象とならない財産 → 生前贈与で加算
という意味です。
相続時精算課税を選択する前や途中で養子になった場合の内容の続きの文章ですので、これらに該当する人が相続などにより財産を取得しなかった場合であっても、という意味なのでしょう。
続きを確認してみましょう。
(注) 当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産について、法第21条の16第3項第2号の規定の適用により相続税の課税価格に算入する金額がない場合においても、当該被相続人から加算対象期間内に贈与により取得した財産(相続時精算課税の適用を受ける財産を除く。)があるときは、当該相続時精算課税適用者については、法第19条第1項の規定の適用があることに留意する。法第21条の16第3項第2号の規定は、特定贈与者から相続などで財産を受け取らなかった相続時精算課税を選択した人の基礎控除(110万円)の取扱いです。
例えば、贈与で受け取った財産の金額が100万円の場合、基礎控除110万円をマイナスすると、相続税の計算に追加する金額が0円となります。
この場合であっても
・相続時精算課税の適用がある財産 → 相続時精算課税で加算
・相続時精算課税の適用がない財産 → 生前贈与で加算
となります。
今回確認した基本通達は、
・相続時精算課税
・生前贈与の加算
の規定を比較したものとなりますので、実際に適用(計算)する場合は、個別に規定を確認した方がいいでしょう。
—
最近の新しいこと
・S&B 噂の名店 南インド風チキンカレー