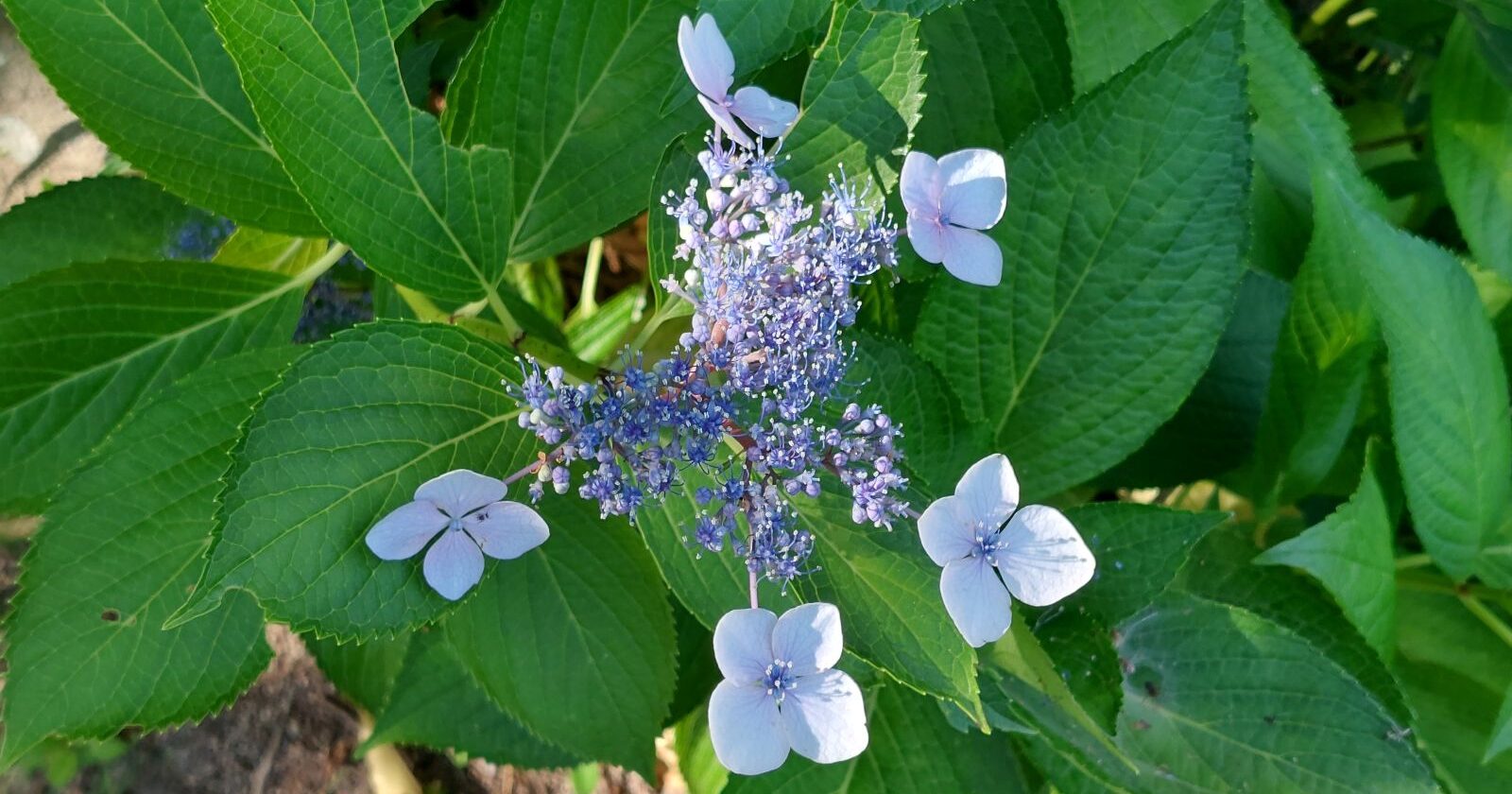今回は、相続などで財産を取得しなかった場合の相続時精算課税と相続税の20%加算を確認してみましょう。
相続税の20%加算
亡くなった方(被相続人)の財産は、孫やひ孫が相続できます。ただし、孫やひ孫が財産を相続した場合、相続した孫やひ孫の相続税が20%増えます。
参考規定
(相続税額の加算)
相続税法第18条、令和7年6月1日施行
第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
2 省略
相続時精算課税との関係
贈与税を相続のときに精算する方法(相続時精算課税)を選択した場合、
・贈与した財産の金額
・贈与税など
が相続税の計算に追加されます。
この追加される規定(読替規定)に、相続税の20%加算があります。
相続税の20%加算に関する読替規定を確認してみましょう。
第十八条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、実際に読み替えてみましょう。
(相続税額の加算)
第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない。ただし書き(20%加算されない場合)が追加されます。
贈与により財産を取得したタイミングで、亡くなった方(被相続人)の一親等の血族(例、子)の場合は、一定の相続税については、この限りでない。
となります。
20%加算の対象から外れるという意味です。
相続税の20%加算は、相続などのタイミングで一親等の血族に該当すれば対象から外れます。反対に、一親等の血族に該当しなければ相続税の20%加算の対象となります。判定のタイミングは、被相続人が亡くなったときです。
相続時精算課税の贈与については、贈与のタイミングで判定します。
そのため、
・一親等の血族に該当する贈与
・一親等の血族以外に該当する贈与
の2つに分かれます。
贈与のタイミングで一親等の血族に該当する場合は、相続税の20%加算の対象から外れることになります。
相続税の20%加算の対象から外れる金額
贈与のタイミングで一親等の血族に該当する場合の計算方法については、相続時精算課税を選択した人が
・相続などで財産を受け取った場合
・相続などで財産を受け取らなかった場合
の2つで変わりません。
参考リンク、相続などで財産を受け取った場合の取扱い
・相続時精算課税と相続税の20%加算
相続税法施行令第5条の2の2
「相続税額の加算の対象とならない相続税額」の規定で、
・法第21条の15第2項(相続などで財産を受け取った場合)
・第21条の16第2項(相続などで財産を受け取らなかった場合)
の規定により読み替えて適用される法第18条第1項(相続税の20%加算)に規定する相続税額として政令で定めるものは、
と規定されていますので、計算方法は同じです。